今回は都合により「メディア美学書」本編(対談)はお休みさせて頂きます
 ビエンナーレ
ビエンナーレ
という言葉をご存じだろうか。季節柄、鼻がムズムズしてくる響きだが、 「二年ごとの」という意味のイタリア語である。これが美術の世界では、 『二年に一度行われる国際的美術展』を意味する。
岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー IAMASは、 高度なメディア表現者を育てるために1996年に設立された。 その開学前年の1995年7月、記念行事として『インタラクション ‘95』と呼ばれる メディアアートについてのフォーラムと展覧会が開催された。
その2年後から国内外の優れたメディアアート (インタラクティブアートとも呼ばれる)作品を紹介するビエンナーレとして、『 インタラクション ‘97』となり、そして今年も『 インタラクション ‘99』が現在岐阜県大垣市にある ソフトピアジャパンで開催されている(1999.3.5 fri.- 3.14 sun.)。
毎回のインタラクションには、レベルが高くバランスが整った作品や、
新しいメディア表現の胎動を感じるものなど、素晴らしい作品が集められる。
IAMASの坂根厳夫学長がこれまで築き上げてきた「人のネットワーク」によって選ばれた
招待作家には、著名な一流アーティストもいれば、ニューヨーク大学在学中の学生もいる。
アートやテクノロジーを超えて何かを感じる、新しい方向性を持った作品が紹介され、
その可能性、アイデアの力を感じ、逆に「この装置をあなたならどうするか」などと 問いかけてくるような作品もある。
 ギャラリー
ギャラリー
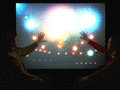
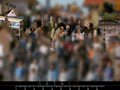
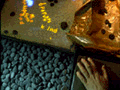
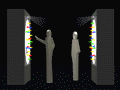
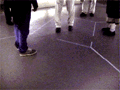
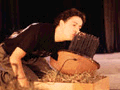
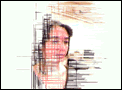
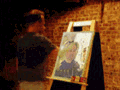

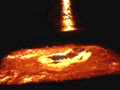
インタラクション ‘99(資料提供:IAMAS)
 メディアアートは21世紀のヒット商品像
メディアアートは21世紀のヒット商品像
なのかもしれない。ミシン、冷蔵庫、車、テレビ、ビデオ、ゲーム機、ゲームソフトと、 20世紀のヒット商品は実用品から非実用品へと変わってきた。
さまざまなメディアを使った表現作品は、80年代から始まった。コンピュータの発展普及
とともに、世界中で多くのメディア・アート、インタラクティブ・アート作品が発表されてきた。
インタラクション ‘99の展示作品に特に限らず、最近の作品傾向としては、コンピュータは裏方に回り、
人の参加をじっと、あるいは淡々と待っているような作品が多い。
人が加わることによって、五感を介したさまざまな表現のやりとりがあり、人と装置が
一体となって作品として完結する、といったようなものである。
このときの、『アナログ感覚をつなぐ巧妙なインターフェイスの工夫』 (展覧会趣旨より引用)によって、心地よさや、優しさ、融通さが無意識に作品への
親近感や好感度へとつながっているようだ。
ソニー創始者のひとり、故井深大氏は「21世紀は心の時代」という言葉を残しているが、 現在のメディアアート、インタラクティブアート作品の中には、 実は21世紀のヒット商品の種があるような気がする。
 この展覧会は、企画
この展覧会は、企画
からカタログ・ホームページ制作、展示構成、運営までのほとんどの作業を、 IAMASの教員・事務のスタッフと学生たちで担当する手作りのイベントだ。 一専門学校で、日常の授業をこなしながらここまでできる。 そして、自由にカリキュラムや単位の設定ができる専門学校だからこそ、 こうした素晴らしい作家の方々との交流の機会、時間を作りやすいのだ。
実は私たちは、これまでIAMASの教員招聘やカリキュラム作成といった開学準備、 システム構築などの支援を行ってきた。 IAMASが開学してから3年が経ち、こうした一つ一つの積み重ねから、 21世紀の新しい学校像がようやく見え始めてきた。
IAMASには高校、大学、大学院からの進学者ばかりでなく、新しい可能性に 再び挑戦するために入学する社会人も少なくない。それもこの学校のアクティビティを支える 原動力の一つである。
社会や教育体系の枠組み、政治、業界の柵に捕らわれることのない、 自由な発想によるイベントの企画制作も、これからの理想的な学校像の一面なのである。 技術ばかりでなく社会や産業の構造がものすごいスピードで変わっていく今、 さまざまな意味で人を回帰させるようなリカレント教育施設がますます必要に思う。




IAMAS(資料:株式会社三菱総合研究所)





参照リンク